「昔は20代で車を持って当たり前だったのに、今は誰も買わない」と感じたことはありませんか?
実際、自動車の保有率や新車販売台数を見ると、20〜30代の車所有率は過去20年間で大きく減少しています。
一方で、「まったく車に興味がない」というよりも、“持たない選択”を意識的にしている若者が増えているのです。
この記事では、経済・社会・文化の面から「なぜ若者の車離れが進んでいるのか」を掘り下げ、これからのクルマとの付き合い方を考えます。
結論

若者の車離れは単純な“流行”ではなく、次の3つの要因が絡み合って起きています。
- 車を持つ経済的余裕がなくなっている(コストの問題)
- 車の価値そのものが変化している(価値観の問題)
- 社会・都市構造が車を必要としない方向に進んでいる(構造の問題)
これらを順番に詳しく解説していきます。
車の維持費が高すぎるという現実

若者が車を「買わない」のではなく「買えない」と感じる最大の理由が、維持費の高さです。
車を所有すると、次のような費用がかかります。
- 自動車本体価格(軽自動車でも150万円前後〜)
- 自動車税や重量税などの税金
- 自賠責・任意保険
- ガソリン代(燃料費の高騰も影響)
- 車検やメンテナンス費
- 駐車場代(都市部では月2万円以上)
これらを合計すると、年間で30〜50万円以上の出費になることもあります。
一方で、物価上昇や住宅費の高騰、給与の伸び悩みなどから、可処分所得は減少傾向。
結果として、「車よりも生活費や趣味にお金を使いたい」という選択が増えています。
都市部では車が必要ない生活ができる

もうひとつの大きな要因が、生活インフラの変化です。
特に東京・大阪・名古屋などの都市圏では、電車やバスが充実しており、通勤・通学・買い物のすべてを公共交通でまかなえます。
さらに、Uber・タクシーアプリ・電動自転車・カーシェアなど、“移動手段の多様化”も進んでいます。
つまり、都市で暮らす若者にとっては、車が「必需品」ではなく「贅沢品」になっているのです。
また、渋滞や駐車場探しのストレスを考えると、「車を持たないほうが自由」という声も多く聞かれます。
価値観の変化「モノ消費からコト消費へ」

昔は「車を持つ=大人の証」「社会的ステータス」でした。
しかし今の若者は、所有より体験を重視する傾向があります。
たとえば、次のような変化が起きています。
- 車よりも旅行やライブ、カフェ巡りにお金を使う
- 高級車よりも“推し活”や“デジタルガジェット”に興味
- SNSで共有できる体験やストーリーを重視
つまり、「車を持つこと」よりも、「車で何をするか」「その時間をどう過ごすか」が重要なのです。
これにより、車は“夢の象徴”から“ツール”へと位置づけが変化しました。
デジタル時代が移動の価値を変えた

かつて車を持つことは、「自由」と「娯楽」の象徴でした。週末には友人や恋人とドライブに出かけ、景色を楽しみながら非日常を味わう——そんな時間が、多くの人にとって特別な体験だったのです。
しかし今では、スマートフォン1つで世界中の情報・人・コンテンツにつながる時代になりました。YouTubeやNetflixなどの動画サービス、SNSでの交流、オンラインゲームといったデジタルコンテンツが「外出しなくても充実できる」環境を生み出しています。家の中で完結する楽しみが増えたことで、移動の価値そのものが相対的に低下しているのです。
特に若い世代では、「出かける=コストがかかる」と考える傾向が強まっています。燃料代、高速料金、駐車場代などを払ってまで外出する必要性を感じにくくなり、“移動の目的”が明確でない限り、車を使う理由が見いだせないのです。
さらに、働き方のデジタル化もこの傾向を後押ししています。リモートワークやオンライン会議が普及したことで、通勤や出張といった「仕事のための移動」が減少しました。以前は「通勤があるから車が必要」という考え方が一般的でしたが、今では在宅勤務が主流になりつつあり、「車を持つ必然性」はますます薄れています。
また、オンラインでの買い物も日常化しました。食料品から日用品、家電、ファッションまで、すべてがスマホ1つで自宅に届きます。つまり、移動しなくても生活が完結する社会構造が出来上がっているのです。
その結果、「車を持つこと=便利」だった時代から、「車がなくても不自由しない」時代へと変化しています。今の若者にとって車は、生活の必需品ではなく“持たない選択肢の一つ”になっているのです。
カーシェア・サブスクの普及が「所有の意味」を変えた

今の若者は、「車を持たないけど、必要なときに使う」スタイルを選んでいます。
カーシェア・サブスクリプションサービスが広がったことで、
購入しなくても、利用体験を簡単に得られるようになりました。
特に都市部では、
- スマホ1つで予約
- 15分単位で利用可能
- ガソリン代込み
といった手軽さが人気です。
「所有=重い」「シェア=スマート」
この意識が、新しいクルマ文化を形成しています。
環境意識の高まりが車選びを変えている

Z世代を中心に、環境問題への関心が生活の一部として根付いていることが、車離れの背景にあります。
彼らにとって「エコ」は単なる流行ではなく、価値観そのものです。
SNSやニュースで頻繁に取り上げられる気候変動・温暖化・CO₂排出問題などが、日常的に意識されるようになりました。特にZ世代は、小学校や中学校の授業からSDGs(持続可能な開発目標)に触れてきた世代です。そのため、「移動手段を選ぶ=環境にどう影響するか」という視点を自然に持っています。
その結果、「車を所有すること」よりも「環境に負担をかけないこと」を優先する人が増えています。
ガソリン車よりも公共交通機関・カーシェアリング・電動自転車・EV(電気自動車)などを選ぶ傾向が強まっています。特に都市部では、「必要なときだけ乗る」「共有で済ませる」という考え方が一般的になりつつあります。
さらに、Z世代は企業やブランドの環境姿勢にも敏感です。
「環境に配慮していないメーカーの車には乗りたくない」と感じる層も存在し、購入動機が「性能」や「デザイン」だけでなく、「社会的責任」や「サステナビリティ」へとシフトしています。
このように、環境への配慮は単なるトレンドではなく“当たり前の基準”となっています。
「地球に優しいかどうか」が車選びの新しい判断軸となり、所有そのものを見直す動きが広がっているのです。
経済的不安と将来への慎重さ

若者が車を買わない背景には、将来への不安もあります。
- 給与が伸びない
- 物価が上昇している
- 結婚や住宅購入のハードルが高い
こうした現実の中で、「今大きな買い物は避けたい」と考えるのは自然なことです。
また、リース・サブスク・中古車シェアなど、“一時的な利用”の選択肢が豊富なため、
「とりあえず所有しておこう」という感覚も薄れています。
これからのクルマとの付き合い方

若者が完全に車から離れたわけではありません。
むしろ、「新しい形で関わる」時代に入ったといえます。
たとえば、
- EV(電気自動車)でのサステナブルな旅
- 車中泊・キャンプ・ワーケーションなど“体験型”の利用
- シェアカーを使った週末ドライブ
- メタバースやARを使った“仮想カーライフ”
車が「持つもの」から「共有し、楽しむもの」へと変わりつつあります。
まとめ

若者の車離れは、経済・社会・価値観の変化による必然的な結果です。
- 維持費が高く、経済的に負担
- 都市では車が不要
- 価値観が「所有」から「体験」へ
- デジタル・サブスク文化の普及
- 環境意識の高まり
これらを総合すると、「車を持たない」という選択は合理的かつ時代に合った生き方といえるでしょう。
しかし一方で、自由に動ける・人とつながれる・体験を共有できるという車の魅力は、今も変わりません。
これからは、「所有」ではなく「どんなふうに関わるか」を選ぶ時代です。
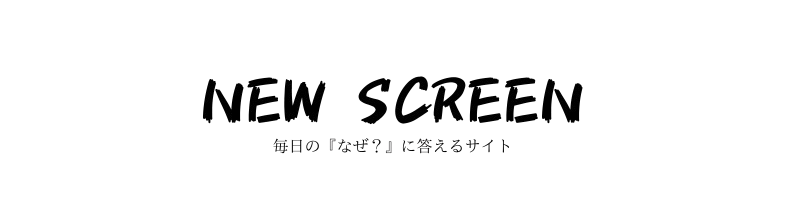



コメント